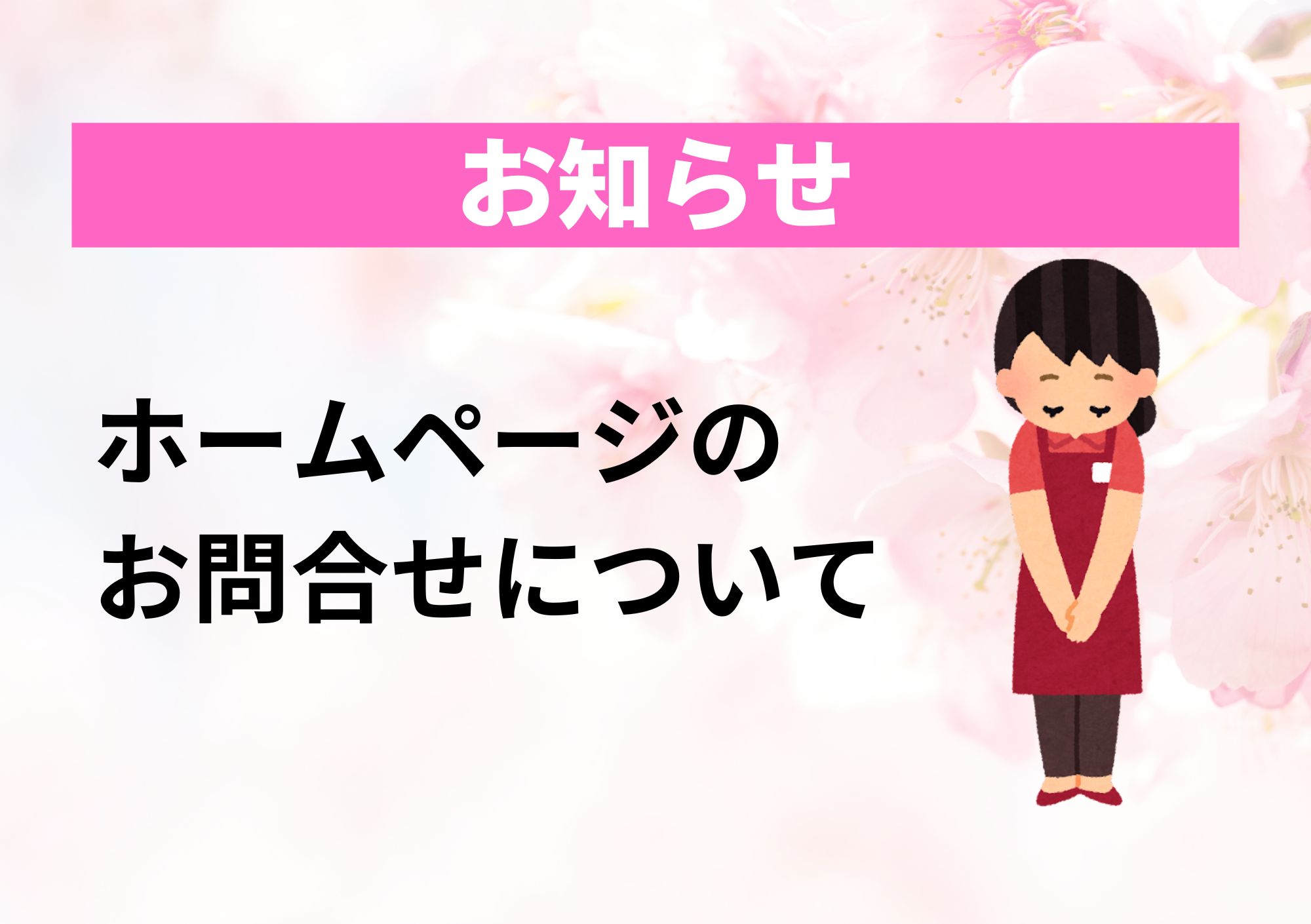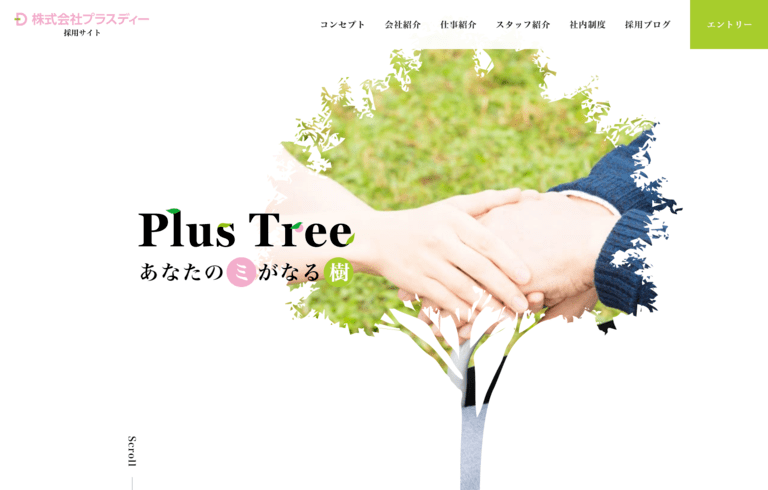以前に、災害時や感染症拡大時のBCP(事業継続計画)についてお話させていただきました。
今回は、災害対応についてBCPと実際にあった災害時の対応を含めてお話させて頂こうと思います。
1訪問介護・訪問看護はどんなお仕事?
災害時の対応をお話させていただく前に、まずは訪問介護・看護がどんなお仕事かをお話させていただきます。
〇訪問介護
利用者様のご自宅に伺って、食事、清拭、排せつ介助や買い物、食事の準備、掃除など生活の介助を行います。
訪問介護は、特に生活援助については同居家族がいる場合には利用できないことがあります。
逆に言うと、独居の方にとっては生活の要になります。
〇訪問看護
利用者様のご自宅に伺って、体調の観察、薬の管理、病状に対する看護処置を行います。
特に、点滴、経管栄養など挿管されている場合や酸素療法を利用されている場合は、看護師の処置が必ず必要になり、介入されない場合は命に関わります。
以上のように、どちらも命に関わる「インフラ」と言えるのではないでしょうか?
2災害時はどうするの?
災害時にどう動くのか、それを計画するのが災害BCPになります。
地震、洪水、暴風災害の際など、どこまで対応するのか、できるのかを計画を立てておくのがこのBCPになります。
実際の事業所の取り組みを紹介しますね!

3地震
地震は急に起こりますよね。その際に考えられるのは、
・通信の混乱
・交通機関の混乱
・建物崩壊の危険
・ライフラインの寸断
さらに訪問時に考えられるのは、
・利用者、スタッフの怪我
まず、仕事中に災害に見舞われたとして備える必要があるのは
・スタッフ、利用者の安否確認
・建物崩壊のリスクがある際の避難場所の確認
ですね。

安否確認の手段として、SNSの活用と伝言ダイヤルの利用を進めています。
同時に、事務所、病院、避難場所といった主に必要になる電話番号をスタッフに携帯してもらっています。
特に、酸素治療を行っている方など医療処置が必要な方に対して福祉避難場所の確認や酸素ボンベをどれだけ持っていく必要があるか等を酸素の機械の横においてもらうようにしています。
4洪水・暴風
洪水・暴風は天気予報などである程度予測をしてくれます。
なので、予測がでるとまず可能な方は訪問調整をして当日の訪問件数を極力減らします。
スタッフの安全も守る必要がありますので。
次に極力出勤人数を減らします。また、比較的安全に出勤できる人で車も利用しながら安全に訪問を実施します。

5もし災害が起こったら...
このように、スタッフと利用者さんの安全と健康をできるだけ守れるようにしながら対処しています。
災害は起こらないのが1番いいのですが、東北地方太平洋沖地震や能登半島地震、西日本豪雨もありました。
まったく無関係にはいられません。起こったときにどうやって身を守るのか、それは日ごろの備えにかかっていると思います。